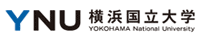沿革
化学・生命系学科の歴史
1949年(昭和24年)より
工学部が設置された1949年(昭和24年)に、化学工業科・電気化学科としてスタートしました。
- 化学工業科
- 電気化学科
1956年(昭和31年)より
カーバイド化学研究施設設置
1962年(昭和37年)度より
化学工学科設置、化学工業科を応用化学科と改称。
- 応用化学科
- 電気化学科
- 化学工学科
1965年(昭和40年)より
カーバイド化学研究施設を材料基礎工学研究施設と改称
1967年(昭和42年)度より
安全工学科が設置されました。
- 応用化学科
- 電気化学科
- 化学工学科
- 安全工学科
1975年(昭和50年)より
材料基礎工学研究施設をエネルギー材料研究施設と改称
1977年(昭和52年)度より
電気化学科を材料化学科と改称
- 応用化学科
- 材料化学科
- 化学工学科
- 安全工学科
1985年(昭和60年)度より「物質工学科」に
1985年からはエネルギー材料研究施設を組み入れ「物質工学科」として、以下の7つの教育研究分野の体制で、1997年(平成9年)まで運営されました。
- 物性化学
- 合成化学
- 材料化学
- 化学プロセス工学
- 安全工学
- エネルギー工学
- 生物工学
1998年(平成10年)度より
4つの【大講座】体制で教育が行われてきました。
- 機能物質化学大講座
- 化学生命工学大講座
- 化学システム工学大講座
- 環境エネルギー安全工学大講座
2007年(平成19年)度より
機能物質化学と化学生命工学を「化学コース」に、化学システム工学、環境エネルギー安全工学を「物質のシステムとデザインコース」に統合し、新たに「バイオコース」を加えた3コース制での教育を開始しました。
- 化学コース
- 物質のシステムとデザインコース
- バイオコース
2011年(平成23年)度より
工学部から理工学部への改組に伴い、それまでの学科「物質工学科」は「化学・生命系学科」となり、「化学コース」を「化学教育プログラム」、「物質のシステムとデザインコース」を「化学応用教育プログラム」、「バイオコース」を「バイオ教育プログラム」とし、さらには教育人間科学部地球環境課程の化学関連の教員も参加して、新たにスタートしました。
- 化学教育プログラム
- 化学応用教育プログラム
- バイオ教育プログラム